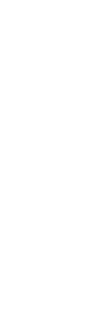子供の独立後に趣味の部屋をつくりたい!最適なタイミングや注意するポイントは?

子供が県外進学や就職などをきっかけに家を出て独立すると、親としての役割も減り、これからの人生を豊かにしたい、自分の時間や趣味を大切にしたい、と感じる方もいらっしゃるでしょう。セカンドライフへの準備、夫婦それぞれのプライベート空間を持ちたいなどの理由で子供部屋を趣味の部屋に変える場合、どんなタイミングで進めていくのがいいのでしょうか。今回のコラムでは、趣味の部屋づくりの進め方、趣味の部屋はどんなテーマがあるか、注意点などもご紹介していきます。
目次
1. 子供部屋を趣味の部屋に変えるときの進め方
子供が高校や大学進学で地元を離れる際は、「しばらく子供部屋はそのまま残す」パターンも多いことでしょう。進学のために一度は実家を離れても、就職と同時に地元に帰ってくることもあるためです。子供部屋はいつまで残すべきか、趣味の部屋にかえるときはどう進めていくのがいいのでしょうか。
1-1.子供部屋はいつまで残す?最適なタイミングは?
子供部屋を趣味の部屋に変えるのに最適なタイミングは、「子供が実家から完全に独立したとき」です。大学卒業、就職や転勤、結婚などで住所を移すとき、親子共に"これから離れて暮らしていく"という意識が高まります。そうした機会に、家に置いてある子供の荷物を本人が整理できて、部屋が空になってから始めましょう。もちろん、ご夫婦で気持ちの切り替えができたタイミングで、まずはどうしていきたいのか相談するのもお忘れなく。
1-2.子供との相談や進め方は?
 子供にとって、実家に自分の部屋がなくなるというのは、利便性だけでは割り切れない感情もあるでしょう。例えこの先暮らすのは夫婦二人だとしても、勝手に決めることはせず、親子で話し合うことが重要です。
子供にとって、実家に自分の部屋がなくなるというのは、利便性だけでは割り切れない感情もあるでしょう。例えこの先暮らすのは夫婦二人だとしても、勝手に決めることはせず、親子で話し合うことが重要です。
ステップ1:部屋の役割変更を提案、合意してもらう
子共部屋をセカンドライフのための部屋にしたい、と前向きな計画として提案します。ただし、帰省の際は泊まる部屋が必要になるため、「客室としても使えるようにする」「帰省した際は別の部屋に泊まれるようにする」などと伝え、帰る場所がなくなるわけではないことを明確にすると、お子さんも安心します。お子さんの合意が得られたら、いつ頃に変更するかを決めて、今置いてある物の整理の話にうつりましょう。
ステップ2:「残すもの」を仕分けしてもらう
部屋にある私物(本やコレクション、思い出の品、家具など)は、お子さん本人に「持っていく」「実家に置く」「処分」の判断をしてもらいます。この時、「実家に置く」ものについて、期限や量を限定し、クローゼットの一部やトランクルームなど専用の保管場所も決めるのがポイントです。学習デスクやベッドなどの大型家具は部屋にあるとかさ張ります。「処分」にも費用がかかり、運ぶのも大変なため、出来れば実家を出ることが決まったタイミングで確認しておきましょう。
ステップ3:趣味部屋への改装・準備
お子さんの荷物が部屋からなくなり、空になったら、リフォームの手配や家具の配置を始めます。夫婦それぞれのプライベート空間を持つ場合も、どんな部屋にするのか、費用はどのくらいかけるのかなど、事前に夫婦で話し合って決めましょう。
1-3.トラブルを避けるために注意したいこと
子供がすぐに部屋の物を片付けることが出来ない場合も、子供のものを無断で処分するのは厳禁です。本人にとっては大切な思い出が詰まっていた物を捨ててしまうと、親子関係にひびが入ってしまうかもしれません。期限を明確にしつつ、それでも子供が忙しくて片付け出来ない場合も、電話やメール等で必ず本人に判断をゆだねましょう。
また、趣味の部屋が完成しても、お子さんが帰省した際に泊まれるよう、ソファベッドや布団の収納スペースがどこかに必要です。泊まれる場所も考えた上で計画を立てていきましょう。部屋のリフォームをする場合、再び子供と同居したり孫が増えて客室が手狭になったりといった変化も見据えて、柔軟に用途を変えられるようシンプルな内装にするのがおすすめです。
2.どんなテーマがいい?50代におすすめの部屋づくり
最初から「こんな趣味の部屋が欲しい!」と明確な方もいれば、夫婦それぞれの部屋をつくろうと決めただけで「実際どうしよう...?」とイメージが膨らまない方もいらっしゃるかもしれません。ご紹介するテーマは一部ですが、参考になれば幸いです。
2-1.癒しとくつろぎのリラックスルーム
 映画鑑賞、音楽鑑賞が好きな方は、シアター&ミュージックルームにしてはいかがでしょうか。プロジェクターや音響設備を導入して、間接照明やリクライニングチェアも置くと、ゆったり寛げる空間に早変わり。リフォームで天井や壁のクロスを貼り換えると、スクリーンがなくてもプロジェクターを楽しめるかもしれません。
映画鑑賞、音楽鑑賞が好きな方は、シアター&ミュージックルームにしてはいかがでしょうか。プロジェクターや音響設備を導入して、間接照明やリクライニングチェアも置くと、ゆったり寛げる空間に早変わり。リフォームで天井や壁のクロスを貼り換えると、スクリーンがなくてもプロジェクターを楽しめるかもしれません。
また、読書が趣味の方や家で仕事したい方、大人の学び直しを楽しみたい方には、壁一面が本棚の書斎もおすすめです。上質なデスクとワークチェア、落ち着いた照明の設置で、集中できる空間に。壁面の本棚は高さが変えられる可動棚の造作にすると、将来的に部屋の使い方が変わった時にも困らないかもしれません。
2-2.ものづくりやコレクション等に没頭できる部屋
 編み物やミシン、絵画、陶芸、模型作りなど、手作業を趣味にしていると、趣味の道具や材料が増えていくものです。大きな作業台を設ける、道具や材料を整理して収納できる棚があると便利でしょう。
編み物やミシン、絵画、陶芸、模型作りなど、手作業を趣味にしていると、趣味の道具や材料が増えていくものです。大きな作業台を設ける、道具や材料を整理して収納できる棚があると便利でしょう。
プラモデルやフィギュア、模型、ヴィンテージ雑貨、カメラなどをコレクションしている方なら、中が見えない収納棚やクローゼット収納よりも、ディスプレイが楽しめる部屋だと良いですね。机も一体になった造作棚を設けたり、埃がかぶらないガラス戸のショウケースに並べて飾ったり、コレクションを飾るのは小さな子供がいないセカンドライフだから出来る楽しみかもしれません。
2-3.心や体を整えるためのリフレッシュ空間
 トレーニング器具を使って自宅で気軽に運動したい方、ヨガやストレッチ等をする習慣のある方であれば、トレーニングや体のケアに集中できる空間はいかがでしょうか。シンプルな部屋に大きな鏡を置いて、あとは必要なマシンやヨガマット、バランスボールなどを並べれば、マイ・フィットネス・ルームの完成です。
トレーニング器具を使って自宅で気軽に運動したい方、ヨガやストレッチ等をする習慣のある方であれば、トレーニングや体のケアに集中できる空間はいかがでしょうか。シンプルな部屋に大きな鏡を置いて、あとは必要なマシンやヨガマット、バランスボールなどを並べれば、マイ・フィットネス・ルームの完成です。
お茶や生け花、書道など和の文化を楽しみたい方は、和モダン空間へのリフォームもいいでしょう。洋室を和室に変えるとまでいかなくても、クロスの貼り換えやカーテンの変更、和紙の照明を使うなど、ちょっとしたリフォームやインテリアの工夫で雰囲気も変わります。
3.趣味の部屋づくりで、忘れてはいけない対策
ご自宅によって間取りは異なりますが、2階建ての戸建てなら子供部屋は2階のことが多いでしょう。趣味の部屋づくりは、その目的や利用頻度にあわせた対策をしないと、かえって楽しめなくなってしまうことも。趣味の部屋づくりの際に気を付けたいポイント、対策とは、どんなものがあるでしょうか。
3-1.階段の安全対策
年を重ねるほど階段は体に負担がかかり、家庭内の事故が増える場所です。利用頻度が高い場合は毎日何往復もすることになって、かえってストレスを感じる可能性も。しばらくは平気だったとしても、将来を考えて階段に手すりをつける、滑り止めを設置するなど、安全対策も検討しておきましょう。
3-2.趣味のアイテムの収納や持ち運びの対策
例えば陶芸用の土など重い材料を運ぶ必要のある趣味の場合、2階まで運ぶのは大変です。また、日常的に使う本や道具などを2階の趣味部屋に持っていくと、使う度に取りに行くことになり生活動線が悪化します。たまに使う趣味のものは2階の趣味部屋に、重いものは1階に収納するなど、動線もよく考えて物の配置を決めましょう。
3-3.快適さや音、振動などの対策
住宅の断熱性能にもよりますが、2階は1階より夏は暑く、冬は寒くなりがちです。きちんと対策をしないと結局その部屋を使わず、物置き部屋になってしまうかもしれません。また、楽器の演奏やDIYなど音や振動が出る場合、1階で生活している家族や近隣住宅への配慮も必要です。防音壁や内窓の設置、クッション性のあるマットを敷いて振動対策をするなど、部屋づくりの際にあわせて対策を考えましょう。
4.体力のある今の楽しみはもちろん、老後の生活も考えた部屋づくりを
子供が独立したことをきっかけに子供部屋を趣味の部屋にするのは、これからの時間を前向きにとらえられるいい機会です。ただし、2階に趣味の部屋を設ける場合、体力のあるうちは趣味を満喫できるプライベート空間として楽しむとして、老後は可能な限り1階で生活できるように物の移動が必要になる可能性もあります。階段の行き来が大変になってから家具の大移動や大規模な整理が必要にならないよう、将来も考えて計画を立てることをおすすめします。
趣味の部屋づくりでリフォームも考えるなら、プロにあれこれ計画を相談した方が早いかもしれませんね!
執筆:ライターY